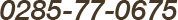こうするべきだ、とアタマでは解っているのに実行できない、ってコトありますよね。
「禁煙するべきだと解っているのに禁煙できない」とか「運動するべきだと解っているのに運動できない」とか「勉強するべきだと解っているのに勉強できない」とか。
本当にそうしたいと思ってるのに。
イヤもうやるしかないって解ってるのに。
それでも、どうしても実行できない。
こういった「わかっちゃいるけど、やめられない、あるいは、やれない」という傾向を、私のブログでは「努力できない病」と呼んでいます。
なぜ、このような「努力できない病」になってしまうのか?
一般的には、その理由として「人間の弱さ」だの「ナマケモノだから」とか、そんな風に言われがちですが、本当はこれはメンタルヘルスの問題なのです。
そして、この「努力できない病」にかぎらず、「すべてのメンタルヘルスの問題は道徳の問題である」というのが、エーリッヒ・フロムの精神分析理論になります。
ただし、フロムの言う道徳というのは一般的な意味での道徳とは、かなり違うものです。
そして一般的な意味での道徳と、フロムが言うメンタルヘルス上の問題を解決するために必要な「人間的な道徳」との違いを、ハッキリと理解できていないと「努力できない病」を治すのは、とても難しくなります。
フロムがいう「人間的な道徳」において、もっとも道徳的な行為とは「自分自身の成長と幸福のために行う行為」であり
まったく道徳的ではない行為は「自己破壊的な行為」のことです。
つまり一般的な意味での道徳では、ほめられるコトの多い自己犠牲的な行動は、もしもその自己犠牲が自己破壊と同じものであるなら人間的な道徳で言えば、まったく道徳的ではナイ行動なのです。
逆に言えば、自己犠牲的な行動ではあっても、それが、まったく自己破壊的な行動ではナイ場合は、人間的な道徳においてもその自己犠牲的な行動は道徳的と言えます。
たとえば、普通選挙制が確立していない社会において、自分が心から支持する候補者に投票することが、自分の社会的な立場を危うくするような場合に行われる自己犠牲的な行動について考えてみましょう。
この時、自分の信念を優先するにせよ、社会的な立場を優先するにせよ、自分の一部を犠牲にする必要が出てきます。
この時に自分の社会的な立場を犠牲にし、自分の信念を優先する場合、一見、自己犠牲的な行動をしているように見えるでしょうし、実際に自分の社会的な立場という意味での幸福や成長を犠牲にしていることは事実です。
でも、ここで自分の社会的な立場における幸福や成長を犠牲にするのは、自分の信念に従うことによる自分の精神的な幸福や成長のためなのですから、これは決して自己破壊的な行動ではありません。
つまり、人間的な道徳において自己犠牲的な行動が道徳的でありえるのは、その自己犠牲的な行動が一見自己犠牲的にはみえても、実際はそれが自分自身の幸福や成長のために行われる場合だけなのです。
人間的な道徳では、誤解を恐れずに大胆に言えば、「自分の利益を第一に考える自己愛たっぷりな人こそが、いちばん道徳的な人」なのです。
えええ?それっていわゆるジコチューでは?まるで道徳的な人じゃないでしょ!と思われた方、それはあなたの「道徳」に対する認識に誤解があります。
フロムの言う「人間的な道徳」とは、社会のために一人一人の個人を犠牲にすることを目的とした道徳ではありません。
フロムの言う「人間的な道徳」とは、一人一人の個人としての人間が幸福になり成長するために必要な規則のことなのです。
そしてこの「個人としての人間が幸福になり成長するために必要な規則としての道徳」と一般的な意味で言われる道徳との違いをハッキリと理解していないと、道徳の問題は大きな混乱を招きがちです。
そしてこの混乱こそが「努力できない病」を発病させ、また悪化させる最大の原因なのです。
よって、以下の文章では、この「人間が幸福になり成長するために必要な道徳」=「人間的な道徳」とは何か?について、エーリッヒ・フロムの「人間における自由」を中心として「精神分析と宗教」「自由からの逃走」「愛するということ」などの著作からの抜粋も含めて、それらをなるべく解りやすいように解説を入れながら書いてみたいと思います。
目次
利己主義と自己愛
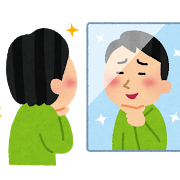
まず利己主義と自己愛の問題から考えましょう。
利己主義は、私たちの社会ではイケナイコトです。
利己主義者であることは罪であり、他人を愛するのが美徳だと私たちは教え込まれています。
けれども現実の社会は、決してこの教え通りには作られてはいません。
現実の社会では、逆にあまりにも利己的でなさすぎるような人、いわゆる「人が良すぎる」といわれるような人は、他人からイイように利用され、かえって馬鹿にされがちです。
現実の人生から私たちが獲得する教訓は、むしろ「多少なりとも利口な人間はみなある程度は利己的なものだ」といった種類のものです。
つまり、現実の社会では、いわゆる「神の見えざる手」こそが、社会をうまく動かしている、という考え方が、大手をふるってまかり通っているのです。
「神のみえざる手」という考え方とは
アダム・スミスが提唱した経済理論で、「人間の最も強力で合理的なエネルギーは利己主義であり、この利己主義という衝動に従って、それぞれの個人が、私利私欲を追及することが同時に公益にも最も良く貢献することになる」といった考え方です。
この「利己主義こそが最大の公益につながる」という理論は、あきらかに欺瞞であり、すでに様々な論者によって誤謬でもあることが証明されていますが、今回はこの点については言及しません。これについてはまた別の機会に書きます。
しかしながら、このような経済理論の誤謬が証明された現在でもなお「利己主義こそが最大の公益につながる」というアダム・スミスの経済理論的な考え方が、お金と権力をもった強者が、まったく思いやりなどもたずに徹底的に利己的にふるまい、弱者をふみにじる弱肉強食的な競争社会を正当化していることは周知の事実です。
だからこそ、明日の食べ物さえない人達がいることを知っていながら、たった一度の月までの旅行に何百億円も費用をかける人達がいることも、道徳的な非難を浴びずに済むのです。
ところがおかしなことに、利己主義は最大の悪であり、他人を愛することが最大の美徳だという、「神のみえざる手」とはまったく矛盾する考え方もまた、私たちの社会の中で同じように大きな影響力をもって存在してもいます。
一つの文化の中で、このように、明らかに矛盾する二つの原理が並んで説かれているということに、私たちは戸惑いますが、それは疑いのない事実です。
この矛盾の一つの結果は、個人の混乱として現れます。
二つの矛盾する教えに引き裂かれて、人は自分の個性を形作るうえで重大な妨害を受けます。
この混乱こそが、現代人の悩みと無力感のもっとも重要な原因の一つです
人は本質的に「悪」なの?
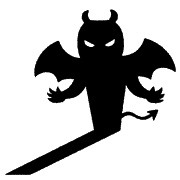
この、わたしたちの社会の中で否定されている「利己主義」は「自己愛」と、ほぼ同義語として用いられています。
つまり他人を愛するという美徳を行うか、自分を愛するという罪を犯すかの2者択一的な問題になっています。
このように「自己愛を否定する道徳」の背後にある考え方は、人間の力を否定し、人間を超人間的な力に依存させがちなプロテスタント的な、あるいは大乗仏教的な考え方です。
これらの教えの本質はこうです。
「人間とは本質的には悪であり無力である。人間は自分の力だけではけっして道徳的に優れた人になることはない。道徳的に優れた人になるためには、自分自身の悪を自覚し、卑下し、神にすがらなければならない。本質的に悪である自分などを愛することじたいが罪だ」
これはまさにスーパー権威主義的とでも言うべき考え方でしょう。
神という完全無欠のスーパースターが前提されている、このような超権威主義的な考え方の中では、神に比べれば、あきらかに悪である自分などを愛することは間違いであり、自分にたいして抱くべき正しい態度は、自己卑下と自己嫌悪だ、というコトなってしまいます。
たしかに、このような考え方の中では、自己愛と他人への愛とは矛盾するものであり、自己愛は利己主義と同じものだと考えられるでしょう。
こういった人間観は近代社会の発展に大きな影響を与えました。
なぜなら、このような視点からは、「自分自身の幸福」が人生の最高の目的とは考えられないからです。
そのために、こういった種類の道徳観は、「一人の人間としての自分自身」というものを「国家や仕事や社会的な成功」といった「自分自身を超えた目的」のための手段にしてしまう生き方を作るうえで、好都合なモノだったのです。
カントはこう考えた

カントは、「人間は自分だけを目的とするべきで、他人の手段になってはならない」という思想によって、啓蒙時代のもっとも影響力の強い倫理思想家でしたが、それにも関わらず自己愛については同じように非難しています。
彼によれば、他人の幸福を願うことは美徳ですが、自分自身の幸福を願うことは道徳とは無関係です。
というのも「自分の幸福を願うことは人間の自然な性質であり、自然な性質というものは、道徳的には積極的な価値をもたない」(「実践理性批判」)とカントは考えるからです。
けれどもカントは、人間は自分の幸福への願いを捨ててはいけない、とも言います。
ある場合は自分の幸福を願う事は義務にすらなります。なぜなら健康や富といったものが、人間が果たすべき義務の遂行に必要になることがあり、また貧乏などの「不幸」が義務の達成を妨げたりすることも有り得るからです。
けれども自己愛じたい、つまり自分自身の幸福を得ようとすることそのものが、それ自体で美徳だということは決してあり得ない、と彼は言います。
自分自身の幸福を追求することは道徳の原理としては「もっとも反対するべき事柄である。それは単にそれが過ちだからというのではなく、…自己愛は道徳の基礎を脅かし、その崇高さをそこなうような効力を与えるものだからである」(実践理性批判)と、カントは言うのです。
カントは人間の完全性を重視しているにも関わらず、どんな専制政治のもとにおいても個人がそれに反逆する権利すらも否定します。
主権を脅かすような反逆は死刑をもって罰せられねばならない、とカントは考えています。
カントは、人間の中には悪へと向かう自然な傾向があると考え、それを強調します。そのためそれを抑える無条件に命令的な道徳が必要だと彼は主張するのです。
ニーチェはこう考えた

啓蒙期の哲学において、一人一人の個人が自分の幸福を追求することの重要性を徹底的に主張したのはニーチェです。
けれどもニーチェもまた「他人への愛と自己愛が二者択一の問題だ」という仮定は共通してもっています。
ニーチェは他人への愛を「弱さであり自己犠牲である」として攻撃し、エゴイズムや利己主義や自己愛(この3つを明確に区別していないためニーチェの論旨にも混乱があります)などを美徳だと主張します。
ニーチェは、愛と利他主義を、「弱さと自己否定の現れ」として非難します。
ニーチェによれば、愛を追うのは自分が欲しいモノのために戦う事のできない奴隷の特色であり、彼らは愛によって欲しいものを得ようとするのです。
こうして利他主義や人類愛はニーチェにとっては堕落の証拠となります。
ニーチェによれば、無数の人間を自分の利益のために犠牲としてもいささかの良心の呵責も感じないということが善であり健康な貴族政治の本質なのです。
このような考え方が、しばしばニーチェの哲学だと理解されてきました。しかしながらそれはニーチェの哲学の本当の核心を代表するものではありません。
ニーチェが「他人への愛と自分自身への愛は矛盾すると信じていた」というのは事実です。けれども彼の見解には、この誤った二分法を克服できるような、ある核心が含まれています。
彼が攻撃する「愛」は人間の「力」からでてくるものではなく、人間の「弱さ」からでてくるものです。
「君たちの言う隣人愛は、君たちの悪しき自己愛にすぎない。君たちは自分自身から逃げ出し、隣人のもとへ行き善行をしようとする。けれども私は君たちの「非利己主義」の底を知っている」(「ツアラトゥストラはこう言った」)とニーチェは述べています。
彼はさらにハッキリと述べています。
「君たちは自分自身の足で立つことができない。君たちは自分自身を十分に愛することができない」(「ツアラトゥストラはこう言った」)
ニーチェにとっては一人一人の個人が「計り知れないほどの大きな意味」(「力への意志」)を持っています。「強い人」とは「本当の親切心と高貴さと、偉大な魂」(「力への意志」)を持っていて、その人は「取るために与えるのではなく、人に勝つために親切にするのではない」「本当の親切とは浪費であり、人格の豊かさが前提される」(「力への意志」)のです。
彼は「ツアラトゥストラはこう言った」の中でも同じ考え方を表しています。「ある者は自分自身を求めて隣人のもとへと行き、またある者は自分自身を失うために隣人のもとへと行く」
この思想の本質は次の点にあります。
愛とは豊かさの表れであり、それは「与えることのできる人間の能力」を前提としています。愛は肯定であり、生み出す力です。「それ(愛)は、愛するものを創りだそうとする!」(「ツアラトゥストラはこう言った」)
ある一人の人を愛することは、それがこの「与えることのできる内的な豊かな力」から出てくるときにだけ美徳となるのであり、それがもし根本的に自分自身というものがないことの現れであるなら悪徳というべきだ、これがニーチェの愛に対する考え方です。
利己主義はダメだ!に注意しよう。

「利己主義は最大の悪であり、自分自身に対する愛は利己主義と同じであり、他者への愛とは矛盾する」という教えは、なにも哲学や宗教の中でだけ、伝えられてきたわけではありません。
それは、家庭でも、学校でも、マスコミでも、本でも、ネットでも、ありとあらゆる宣伝機関を通じて広められている既成概念の一つになっています。
「利己的であってはイケナイ」という言葉は、何世代にもわたって何百万人もの子供たちが言い聞かされた言葉です。
普通、この言葉は「自己中心的で、思いやりがなく、人に関心をもたない態度はイケナイ」ということを意味していると考えられがちですが、実はこの言葉には、まったく別の意味も含まれています。
「利己的であってはイケナイ」という教えには、暗に「自分の望むことをしてはイケナイ、権威者(親や国や会社)のために自分の望みをあきらめなければイケナイ」という意味も含まれています。
利己的であってはイケナイという教えには、その明白な意味とは別に、「自分自身を愛してはイケナイ」「自分自身のために生きてはイケナイ」「自分よりもずっと重要な何かのために生きなくてはイケナイ」という意味も、含まれています。
こうして「利己的であってはイケナイ」という教えは、自発性をおさえ、個性の自由な発展をさまたげるための一番強力なイデオロギーの道具となってきました。
このスローガンのもとで、人間はあらゆる自己犠牲と完全な服従を強いられます。
自分自身のためではなく、自分ではない誰か、あるいは何かのために自分を捨てて仕えるような滅私奉公的な行為だけが「非利己的」なものとされてしまうのです。
フロイトはこう考えた

このように、哲学でも宗教でも一般社会でも唱えられてきた「自分自身に対する愛は、利己主義と同じであり、他人への愛とは矛盾する」という教えは、フロイトのナルシズム説の中でも、科学的な言葉で理論化されてきました。
フロイトは、ある一定量のリビドー(性的なエネルギー)と言うものを仮定しています。
幼児期においては幼児自身がこのリビドーの対象です。フロイトはそれを「第1次ナルシズム」と呼んでいます。
成長するにつれてリビドーは自分自身から「他の対象」へと移っていきます。
この「他の対象との関係」に何らかの問題がおこると、リビドーは他の対象から引きあげられ、その人自身にもどってきます。この状態が「第2次ナルシズム」と呼ばれる状態です。
フロイトによれば、人間が愛を「他の対象」へと向ければ向けるほど、自分に対する愛は減少します。その逆もまた同じです。
彼はこうして「愛」という現象を、自分がもつリビドーを自分から他の対象へ移すこと、としていますので、「愛とは自己愛が減少していくことである」と説明することになります。
ですから、フロイトの理論では、自分自身への愛と、他人への愛との間には根本的に矛盾があり、二者択一的なものである、という結論になるのです。
利己主義は自己愛と同じなの?

けれども、この「自分自身への愛と、他人への愛との間には根本的に矛盾があり、二者択一的なものである」という考え方は、実際の心理学的な観察によって裏付けられるものなのでしょうか?
自分自身への愛は、利己主義とまったく同一の現象なのでしょうか?それとも対立するものなのでしょうか?
また現代人の利己主義は、本当に知的・情緒的・感覚的な多くの可能性をそなえた一人の人間としての自分自身への関心なのでしょうか?
もしかすると、その「自分」とは単に「社会的経済的な役割」の付属品なのではないでしょうか?
論理的に間違っている

実は、現代人の利己主義は本当の意味での自己愛ではなく、逆に本当の自己愛がなくなってしまったことが利己主義の原因なのです。
利己主義と自己愛について、その心理学的な面の検討を始める前に、まず他人への愛と自分自身への愛が両立しないものである、という考え方の論理的な間違いを指摘しておきます。
もしも隣人を一人の人間として愛することが美徳であるならば、私自身もまた一人の人間である以上、私自身を愛することもまた美徳であって悪であるわけがありません。
自分自身を含まないような「人間」という定義はありえません。そのような教えを主張する説は、そのことじたいが既に、その説が矛盾したものであることを証明しています。
聖書の「あなたたちは自分のように、自分の隣人を愛しなさい」という言葉に表されている思想は、自分自身の総合性と独自性に対する尊重や、自分自身に対する愛と理解は、他の人に対する尊重と愛と理解から、切り離すことができないことを意味しています。
自分自身にたいする愛は、他人にたいする愛と、決して切り離すことができないほど強く結びついているのです。
心理学的な前提
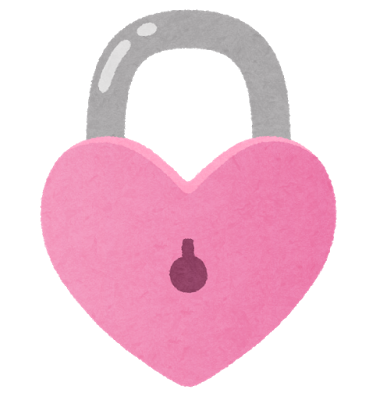
ここで、一つの根本的な心理学的前提を確認したいと思います。
その前提とは次のようなものです。
他人だけではなく自分自身が、自分の感情や態度の「対象」であり、他人に対する態度と自分に対する態度とは矛盾するどころか、けっして分けることのできない連結したものである、ということです。
この前提を今までの議論に当てはめると次のようになります。
「他人への愛と自分自身に対する愛とは二者択一的なものではなく、逆に他人を愛することができるすべての人の中には、自分自身を愛するという態度がみられる。」ということです。
愛する力を切り分けることはできません。もしも愛する力をもっているのであれば、他人を愛することができるのと同様に、自分自身をも愛することができるはずです
愛とは?

「愛」とは、人間の中の創造性(作りだす力・生み出す力)の一つの表現であり、尊敬と配慮と責任と知識を含むものです。
それは誰もが簡単に感じれるような「誰かを好きになるという感情」ではなく、自分自身の愛する能力から出てくるもので、愛する人の成長と幸福のために行う「積極的な努力」であり、その努力なしには感じることができない、きわめて特殊な感情です。
だれもが愛することができる可能性はもっていますが、その実現はもっとも困難な仕事の一つです。
愛するということは、人間がもっている愛する能力の表現であり、誰かを愛するということは一人の人に対して、この能力を具体的に集中することです。
人間が愛することのできる人は世界中でただ一人だけだとか、その一人を見つけ出すことこそが愛を手に入れる方法だ、とかいったロマンティックな考え方は、愛の真実ではありません。
また、もしもそのような人がみつかれば、その人だけを愛して、それ以外の人はまったく愛さなくなる、という考え方も間違っています。
たった一人の人に対してだけ感じるような愛は、まさにそのこと自体がそれが愛ではなく共生的な執着であることを示しています。
人間にたいする愛

「愛する」ということには、「心の底から強く良いと確信する」という意味が含まれています。
愛する人を、「心の底から強く良いと確信する」ということは、一人の人間としての良い特質をその人がもっている、というコトです。
一人の人を愛するということは、人間そのものを愛するということなのです。
人間にたいする愛とは、ある特定の誰かを愛するという経験の後から現れる抽象的な概念だと思われがちですが、実際にはその順番は反対です。
人間にたいする愛という前提があってはじめて私たちはある特定の誰かを愛することができます。
もしも人間自体を愛することができないのであれば、その人は特定の誰かを愛することもできません。
たとえ、本人が自覚的には誰かを「愛している」と信じていたとしても、もしもその人が人間を愛することができないのであれば、そこで言われている「愛」とは、実は依存であったり、支配欲であったり、執着であったり、場合によっては憎悪であることすらあるのです。
このように考えていけば、人間にたいする愛が前提としてあるならば、自分自身も原則的には他人とまったく同様に、愛する対象でなければならない、という結論になります。
自分自身の生活、生命、幸福、成長、自由を、心の底から大切だと確信するためには、自分自身を「愛する能力」が必要です。
それは自分に対する配慮であり敬意であり責任であり知識です。
もしも人が創造的に愛することができるのであれば、その人は自分自身も愛しています。もしも他人しか愛せないのであれば、本当はまったく愛することができないのです。
じゃあ利己的な人ってどんな人?

では、このように自分自身にたいする愛と他人に対する愛がつながっているとすれば、他人への真の関心をまったく持たない利己主義は、どのように説明されるでしょう?
利己的な人は自分自身にだけ関心を持ち、すべてを自分のために欲しがり、与えることに何の喜びも感じず、取ることのみを喜びます。
自分の外側にあるものはすべて、ただ自分がそれから何を取ることができるか?という観点からしか見られません。
この人は他人の欲求には何の関心も持ちませんし、他人の尊厳やプライドになどには何の敬意も払いません。
この人の目には自分しか映らず、愛する力がまったくありません。
このような人がいることが、他人への関心と自分への関心とは、どうしても二者択一にならざるを得ないことを証明している、と思われる方もいるかもしれません。
たしかに利己主義と自己愛とが同じモノであればその通りでしょう。
けれども、この仮定こそがまさに今まで述べてきた多くの誤った結論の原因となってきた誤解なのです。
利己主義と自己愛は、同じものであるどころか実際は正反対のものです。
利己的な人は自分を愛しすぎているのでなく、愛さなすぎるのであって、実際には自分を憎んでいます。
自分自身に対する愛情と関心がないことは、その人に創造性(生み出す力・作りだす力)がないことの表れの一つにすぎません。
そして創造性がナイという事こそが、この人に空虚感と不満感をあたえ続けています。当然、この人は不幸であり、なんとか人生から満足をつかみとろうと必死でもがきますが、自分自身でそのジャマをしています。
この人はあまりにも自分の事ばかりにかまけているように見えますが、実際は本当の自分自身にはまるで心を配っていないため、それを埋め合わせようと無駄なことをしているに過ぎません。
フロイトは利己的な人をナルシス的とよび、あたかもその人が愛を他人へは向けないで、自分自身にだけ向けているように描きましたが、そうではなく、利己的な人は他人を愛せないだけでなく、自分自身も愛することができません。
口うるさい母親に愛はあるか?

このような「本当は自分をまったく愛していない利己主義」というものは、「心配過剰でいちいち子供に指図しなければ気のすまない母親」にみられるような、「自分の関心の対象となる者」に対する貪欲な関心を観察すれば、より解かりやすいでしょう。
この母親は意識的には「自分は子供を溺愛しすぎている」と信じていますが、実際にはこの母親は子供という「自分の関心の対象となる者」に対して抑圧された深い敵意を抱いています。
この母親がやかましすぎるのは子供を愛し過ぎているからではなく、全然子供を愛せないことを、なにかの形でつぐなわなくてはならないからです。
滅私奉公は病気かもしれない

このような「本当は自分をまったく愛していない利己主義」の性質にたいする以上の理論は、神経症的な「滅私奉公的態度」にたいする精神分析の実際の経験に裏づけられています。
この「滅私:無私」という態度はかなり多くの人にみられる神経症の徴候です。
普通この種の病気をもっている人は、この徴候じたいではなく、自分の憂鬱感とか、極端な疲労感とか、仕事上の無能力感とか、愛情関係の破綻などに悩んでいます。
自分の「滅私:無私」的な傾向は、神経症の症状とは感じられないどころか、しばしば、そのような人たちが自分自身の誇りとするような良い性格特性なのです。
この「滅私・無私」的な人たちは、自分のためには何も欲せず、ただ他人のためだけに生きています。そしてこの人たちは自分を重視しないということを誇りにしています。
けれどもそんなに「無私」であるにも関わらず不幸であり、しかも自分の一番身近な人たちとの関係が上手くいかずに困っているのです。
この人たちは、自分の中の病的な徴候を取り除きたいと思っていますが、自分の「無私性」はその中には含まれていません。
この種の人たちに精神分析をしてみると、この「無私性」は、この人たちがもっている他の病的な徴候と別種のものではなく、かえってその中の最も重要な一つであることがわかります。
この人たちは何かを愛したり楽しんだりする能力が麻痺していて、人生に対する敵意に満ち、この人たちの無私性の仮面のすぐ裏側には巧妙に隠された激しい自己中心癖がひそんでいることが明らかになります。
この種の人たちは、自分の無私性が、ほかの問題行動と同じく病的な徴候であることを理解し、この種の「無私性」や他の色々な問題を作り出す原因となっている自分の中の「創造性の欠如」という問題を解決したときにはじめて神経症が治るのです。
献身的な母親は危険です。

このような無私性の性質は、それが他人に与える影響のうちに特に明らかになります。
現代においては特に「無私」な母親が自分の子供達に与える影響の中に、その本当の姿がハッキリと現れています。
この種の母親は、自分の無私性が、子供たちに「愛される」ということが何を意味するかを教え、「愛する」とはどういうことかを学ばせると信じています。
けれどもこの母親の「無私性」の与える効果は、この母親の期待に完全に反するものです。
子供たちは自分が愛されていると確信するときに人が示すような幸福そうな様子をしていません。
それどころか子供たちは常にピリピリと神経をとがらせ、母親の気を悪くすることを恐れ、母の期待通りに生きなければならない、と思いつめています。
子供たちは母親が人生にたいして抱いている隠された敵意に感化されてしまっているのが普通です。それを子供たちは理解するというよりも感じていて、やがてそれに染まってしまいます。
つまり無私的な母親が与える影響は、利己的な母親が与える影響と変わらないどころか、実際には、より悪質な場合さえあります。というのも母親の無私性が母親に対する子供たちの批判を妨げるからです。
子供たちは母親を失望させてはならないという義務を背負わされています。そして子供たちはそれが美徳だという口実で人生を嫌うことを教えられます。
自己愛を持った母親の影響を調べれば、自分自身を愛している母親によって愛される以上に子供に愛や喜びや幸福を体験させるのに役立つものはないということがわかります。
「自分の利益」について

次に考えたいのが「自分の利益」という問題です。
「自分の利益」という問題は、現代社会を考えるうえで鍵となるような一つのシンボルになっています。
この「自分の利益」という考え方には、利己主義と自己愛の問題よりも、さらに色々な意味が含まれています。
なぜ「自分の利益」という考え方に、様々な意味が含まれるようになったのかを十分に理解するためには、この「自分の利益」という考え方が、歴史的にどのように変化してきたのかを考える必要があります。
問題は、本当の意味での「自分の利益」とは何か?
そしてそれはどのようにして決定されるのか?という点にあります。
スピノザはこう考えた

この問題については二つの根本的に違うアプローチがあります。
一つ目はスピノザによって、もっとも明確にされた客観的な考え方です。
彼にとっては「自分の利益を追い求めること」が、もっとも道徳的な行為です。
彼は言います。「それぞれの人が努力して自分の利益を求めれば求めるほど、自分の生活・人生・生命について気をつけることができればできるほど、その人は道徳的な人である。反対に自分の利益を無視するようでは、その人は無能の人である」(「エチカ」)
スピノザの見解に従えば、「自分の利益」とは、自分自身の生活・生命・人生に気をつけること、自分の本質的な可能性を実現すること、ということになります。
「自分の利益」についてのこのような考え方は、「利益」というものを、「何が自分の利益になると感じるのか?」という主観的な感情に従うのではなく、客観的に考えられる人間の性質から言えば、「何が自分にとっての本当の利益になるのか?」という見方からくるものです。
本当の「自分の利益」とは

人間にとっての本当の利益とはただ一つです。
それは「一人の人間としての自分自身が、潜在的にもっている可能性や能力を完全に発展させること」です。
そしてすべての人間は潜在的に「愛する」という能力をもっています。
モチロン他にも色々な能力をもっていますが、この「愛する能力」こそが人間の最も本質的な能力の一つです。(なぜ愛する能力こそが人間のもっとも本質的な能力の一つと言えるのかについてはまた別の機会に書きます。今すぐそれが知りたい方はフロムの「愛するということ」をお読みください。)
よって、この「愛する能力」を発達させることができれば、決して利己的にはなりません。自分の利益を追求することは利己的になることではないのです。
人が誰かを愛するためには、その人とその人の本当の欲求を知らなければならないように、人が自分にとっての本当の利益とは何であり、どうすればそれを得られるのかを知るためには、自分自身を知らなければなりません。
したがって本当の自分と、本当の自分の欲求を知らなければ、「自分の利益」とは何か?という質問に対して、間違った答えを出してしまう可能性があります。
ですから、客観的に妥当な「人間にとっての本当の利益とは何か?」という答えを出すために、心理学や社会学といった人間の科学が必要となってくるのです。
現代版の「自分の利益」

ところが、最近の300年間において「自分の利益」という考え方は、どんどん小さくなっていき、スピノザが考えた意味とはほとんど正反対のものになってしまいました。
それは利己主義と同じものになり、物質的な利益や、権力や成功などにたいする欲望と同じものになってしまいました。
そして以前は道徳と同じであったはずのものが、逆に現在ではその克服が道徳上必要なことになってしまったのです。
このような退化は「自分の利益」について、どう考えるかが、客観的なものから誤った主観主義に変わったために生じました。
こうして、「本当の自分の利益とは何か?」という問題にたいする答えは、人間性と人間の本当の欲求とによって決定される、という考え方じたいが注目されなくなっていきました。
ですから、「何が本当の自分の利益になるのか?」という質問にたいして、人は時に間違った答えを出してしまう可能性がある、という考え方も忘れられてしまいました。
そして「これが自分の利益」だと人が主観的「感じる」ものが、そのまま本当の「自分の利益」なのだと考えられるようになってしまったのです。
権威主義者 VS 進歩的思想家

現代の「自分の利益」にたいする考え方は、二つの矛盾する考え方、権威主義的な考え方と、スピノザ以来の進歩的思想家の考え方の奇妙な混合物になっています。
権威主義的な考え方では、人は「自分の利益」を追求してはならず、自分をただ権威の目的のための道具と考えなければならないと教えます。
進歩的思想家たちはこれに反対して、人はみんな自分自身こそを目的にするべきであって、自分以外の何か別の目的のための手段になってしまってはならない、と教えました。
そこで現代の人々がどうしたかと言えば、実際には権威主義的な行動パターンに従って生きていながら、進歩的思想家たちのように考えたのです。
人は自分のために生きるのではなく、経済機構の、あるいは国家の奴隷となりました。
人は道具の役割を引き受けました。産業の進歩のための道具です。
人は働いてお金を貯めますが、それは自分の生活や人生を楽しむためではなく、それを投資して成功するためです。
ここでは「個人の幸福や喜び」は「人生の本当の目的」ではありません。
けれども、このような「自己否定の原理」にしたがって生きながら、人はこの「自分の利益」を追求しない生き方を、進歩主義的な考え方と混ぜ合わせ、逆にそれこそが「自分の利益」を追求する生き方だと思い込んでいます。
人は「自分の利益」のために行動していると信じていますが、実際には「お金と成功」のために行動しています。
自分にとって本当は一番重要な「自分の人間としての可能性」をまったく満たすことができないままで、自分にとって重要なモノだと感じている、お金や成功を追い求めるうちに、自分自身を見失ってしまっているという事実に、多くの人が気づいていません。
自分とはなにか?その2

「自分の利益」という意味のこのような堕落は、「自分」という概念の変化と密接に関係しています。
中世までの人間は「自分」というものを、血縁的地縁的共同体の一人としてしか認識することができませんでした。
自分とは何か?といえばそれは「〇〇村の百姓で〇〇家の長男である」といった認識の仕方しかできませんでした。
近代以降、人間は自分を一人の個人として経験するという課題に直面し、ここで人間のアイデンティティーが問題となりました。
18世紀から19世紀には、自分という概念はより狭くなり、「自分とは自分の持つ財産である」と感じられるようになりました。
もはや「われ思う、ゆえに我あり」ではなく「われは持つ、ゆえに我あり」となってしまったのです。
市場経済における「自分」

ここ最近約100年の市場の影響の増大によって「自分」という概念は「われは持つ、ゆえに我あり」からさらに変化して「われとは、なんじが我に期待するところのものなり」となりました。
市場経済の中に生きる人間は、自分自身を一つの商品として感じます。
人は商売人が自分の売ろうとしている商品と切り離されているように、自分自身から切り離されています。
確かに人は自分自身に関心をもっています。社会における自分の成功に非常に大きな関心を持っています。
けれどもここでいう「自分」とは、社長、ビジネスマン、アーティスト、として高値で売りつけなければならない「商品としての自分」です。
ここでの「自分の利益」とは、人間市場において最高価格で売らなければならない「商品としての自分にとっての利益」という意味に変わってしまっているのです。
「現代人が自分の利益をどれほど誤解しているか」を、もっとも鋭く描写しているのはイプセンのペール・ギュントです。
ペール・ギュントは自分の全生涯が、自分の利益の実現に捧げられていると信じています。
彼は自分というものを、このように描いています。
「ギュント自身よ!願望と快楽と欲望の軍隊よ!ギュント自身!それは空想と要求と野望に満ちた大海だ!それが私の胸をワクワクさせてくれる!それこそが私が私であるということだ!私が生きる意味だ!」
けれども、その生涯の最後になって、彼は「自分」というものについて思い違いをしていたことに気づきます。
「自分の利益」のために生きていたはずが、「本当の自分の利益が何であるのか」を誤解していたこと、守ろうとしていたはずの自分を「実は失ってしまっていたこと」に気づくのです。
彼は今まで一度も本当の自分であったことはなく、ゆえに、再び原材料として溶鉱炉に投げ込まれなければならないと告げられます。
彼は「自分自身の満足を求めよ」というトロルの原理に従って自分が今まで生きてきたことに気づきます。それは「自分自身の真実を求めよ」という人間の原理の正反対のものです。
彼は「何もない」という恐怖に襲われます。
ニセモノの自分による支えや、成功や所有物が取り去られるとき、あるいはそれらのものが真剣な疑問となるとき、本当の自分というものを持たない彼は、「何もない」という恐怖に倒れてしまいます。
彼は世界中の富を得ようと努力することによって、また自分の利益がそこにあるように見えた金や成功を情け容赦なく追及することによって、本当の自分自身を失ってしまったことを認めざるを得ないのです。
権威主義は利己的じゃない?

全体主義や権威主義的な考え方を持つ人達が、資本主義は利己主義の原理に支配されているゆえに道徳的に正しくない、と主張することがあります。
そして彼らは「自分たちの組織は、一人一人の人間が無私の心で、宗教的な「より高い」目的とか「民族」とか「国家」とかへ服従するということを原理として掲げているから、自分たちのほうが道徳的に優れている」と、主張します。
このような主張が、ある一定の人々の心に訴えるのは事実です。
というのは、多くの人が利己的な関心の追及には幸福がないと感じ、そして漠然とではありますが、人々の間でより大きな団結と相互の責任を果たしたいという願いを描いているからです。
たしかに資本主義は利己主義の原理に支配されていて「神の見えざる手」という欺瞞で、無理やりそれを正当化しているだけ、ということは事実ですし、北欧型の社会民主主義と比べれば、道徳的に正しくないという主張は的を得たものでしょう。
けれども、全体主義者もしくは、権威主義者達の主張には簡単に反論することができます。
第一にそれは一般大衆を征服し支配しようとしている少数の特権階級の極度の利己心を偽装するだけのものであるために真面目なものではありません。
無私という彼らのイデオロギーは、大衆を欺いて少数者の支配に服従させ、彼らの搾取と操縦を容易にしようとする目的を持つものです。
さらに権威主義的なイデオロギーは、国家や宗教団体といったその組織自体には、情け容赦のない私利私欲の追求を許しながら、まるで無私の原理を代表するかのごとく装って論理を混乱させています。
一人一人の個人は、国家のため、宗教あるいは政治団体のために、無私の心で自分を捧げなければなりませんが、その一方で国家や、宗教あるいは政治団体自身は、他の国の幸福や、ほかの団体の幸福などは完全に無視して、「利己的」に自分たちの私利私欲を追求することが許されているのは、明らかな矛盾です。
進歩的思想をダメにしないために

このような権威主義的組織の教えは、「人間はもともと弱く無力なので何かに頼らなければならない」というプロテスタント的な教え、もしくは大乗仏教的な教えの復活です。
このような考え方の克服こそが、近代の精神的・政治的進歩の本質でした。
このような権威主義的イデオロギーは、「個人の独自性と尊厳とに対する尊重」という西欧文化のもっとも貴重な達成を脅かすものです。
また、このような権威主義的なイデオロギーは、現代社会に対する建設的な批判を封じますので、現代社会に必要な変革を妨げるものでもあります。
現代文化の欠陥は、その個人主義の原理や、「自分の利益の追求こそが人間が何よりも優先すべきことである」という考え方にあるのではなく、「自分の利益とは何か」という間違った解釈にあります。
問題は「人々が自分の利益にばかり心を奪われすぎている」という事実にあるのではなく、逆に「人々が自分の本当の利益に十分に心を配っていない」という事実にあります。
また問題は、「人があまりにも自分を愛しすぎている」という点にあるのではなく、逆に「人が自分自身を本当は愛していない」という点にあるのです。
では、「自分の本当の利益に十分に心を配る」ためにはどうすれば良いか?また「自分自身を本当に愛する」ためにはどうすれば良いか?については「がんばれない、努力できないを治すたった一つの方法」をご覧ください。
冒頭にも記載したように、この記事は、エーリッヒ・フロムの「人間における自由」からの抜粋を中心として「精神分析と宗教」「自由からの逃走」「愛するということ」からの抜粋を含めています。興味を引かれた方はぜひ読んでみて下さい。