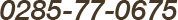親孝行、それはつねに誰にとっても正しいことでしょうか?
モチロンそうではありません。
なぜなら、親の中には自分の子供に暴力をふるいケガをさせたり、強姦したり、殺してしまうような人もいるからです。
「親孝行」とは、辞書によれば「親を敬い、よく仕えること」です。
でも自分を強姦しようとする親や、自分を殺そうとする親を「敬う」ことも、その親に「よく仕えること」も、あきらかに間違いです。
では体罰という名目で、子供に暴力をふるいケガをさせるような親ならば、どうでしょう?
「ケガをさせるのは良くないが、体罰じたいは悪くはない」という意見もいまだみられます。
けれども、本当に子供のためを考えるのであれば、体罰は完全にアウトです。
イヤ、体罰にも少しは教育的な利点があるんじゃないの?と思われる方はこちらをどうぞ→(体罰を禁止するべき科学的根拠 )
体罰がまったく子供のためではないことが科学的に明らかである以上、体罰とはそのまま暴力でしかありません。
ですから体罰をおこなう親に、親孝行することもやはり本質的には正しいとは言えません。
しかしながら現在日本では(国連等から何度も勧告を受けているにも関らず)親の子供に対する体罰は、法的な意味では完全にアウトではありません。
(やっと最近これ、法的にも完全なアウトになりましたねえ。民法に体罰の禁止が明文で記載されたし、懲戒権を定めた条文も削除になりました!万歳!)
もしも自分の子供を強姦したり殺したりすれば、たとえ親であろうと(今では)法的にも通常の強姦罪や殺人罪が適用され、その親は子供を強姦した、もしくは殺した罪で裁かれます。
ただ、それでもやはり問題はあります。
殺されてしまった子供には今更なにもできませんが、強姦された子供はどうなるでしょう?
もちろん、親が強姦罪で逮捕されれば、もうそれ以上はその親とは関わらなくても済みます。
けれども、自分の親から強姦されたという烙印は、強姦された本人には全く非はないにも関わらず、世間の目という点からみれば親不孝という烙印よりも恐ろしいものかもしれません。
また親の体罰によってケガをさせられた場合はどうなるでしょう?
親が自分の子供に暴力をふるってケガをさせたとしても、それはあくまでも暴力ではなく体罰であり、ケガをさせてしまったのは不慮の事故で故意ではない、と正当化してしまえば、法的には過失傷害罪になってしまいます。
そうなってしまえば、子供は自分に暴力をふるいケガをさせるような親とも、その後も一緒に生活しなければならなくなってしまうのです。
このような現状である以上、体罰をおこなう親に対する親孝行は現代日本社会においてはまだ「明らかな間違い」とは言いきれないのが現実でしょう。
(このような状況も前述の民法改正によって、「明らかな間違い」といえるようになったかな?でも法律が変わっても、まだまだ、感情的な部分では体罰正当化する輩は、いなくならなさそうですが。)
このように、法律は変わりましたが、かと言って「親という権威」に、基本的人権を侵害するほどの強い権力が(現実の社会においては)21世紀の現在でも与えられている、という状況はやっぱりあんまり、変わっておらず、やはり今でも、強烈に強い権力が「親という権威」に与えられているのが、日本の実情です。
これほど強力な権威主義社会に生きる現代日本人には、欧米諸国の人々とは比較できないほどの高いレベルで注意しなければならない「努力できない病」の原因となる問題があります。
今回は、この現代日本における「親孝行」と「努力できない病」の関係について、エーリッヒ・フロムの「人間における自由」論旨にそって、その抜粋を中心に考えてみたいと思います。
目次
親を全面否定することは可能か?

「たとえどんな親であろうとも、子供は絶対に親孝行をするべきだ。」と考えるような人は、非常に強い「権威主義的な価値観」を、持っていると言えるでしょう。
しかしながら、たとえあまり強いものではないとしても、現代日本社会のように強力に権威主義的な社会に生まれ育ったほとんどの人はやはり「権威主義的な価値観」を持っています。
そしてこの「権威主義的な価値観」こそが、人間の無力感や不信感を大きくします。
なぜ、権威主義的な価値観が、人間の無力感や不信感を大きくするのか?について良くわからない方は、こちらを読んでからまたココに戻って下さい。→「SMが「努力できない病」を悪化させるのはナゼか?論理的に説明してみた。 」
権威主義的な価値観によって作り出され、そして大きくされてしまった無力感や不信感が「努力できない病」の原因となる「意志の麻痺」を作りだします。
ですから、努力できない病を根本的に治すためには、自分のもっている権威主義的な価値観を変える必要があるのです。
そして、少なくても「非合理的な権威」は全面的に否定する必要があります。(非合理的な権威とは何か?について詳しくはこちらをどうぞ→「権威とはなにか?」)
つまり、たとえ自分の親であろうと、その親が非合理的な権威である場合、「努力できない病」を治すためには、親を全面的に否定する必要がある、ということになってきます。
ところが、いまだ家父長制的な文化が色濃く残り、かつ法律的な面においても強力な権威主義的社会である現代日本社会においては、どれほどヒドイ親であっても親を全面的に否定した場合、子供は、罪悪感を背負うことになるケースがほとんどです。
もしも、そこまでヒドイ親ではなかったとしても、人間である以上、まったく欠点を持たない人など現実には一人もいません。
にもかかわらず、多くの人は自分の親を、まったく批判できません。
また、親の性格や言動のある一部分については、それを親の欠点として批判することができても、肝心の自分がそれによって傷つけられ、被害を受けた親の欠点については、まったく批判できない人もいます。
あるいは、明らかに問題をもっている親であっても、そして、その親の問題点を理性としては認めることできて、その問題点に対して適切な批判をしたり、怒りを抱いたりすることができても、そのような完全に正当な自分の批判や怒りに対して、良心のやましさや心苦しさを感じる人もいます。
親を喜ばせていない罪悪感

さらに、注意しなければならないのは「自分は親を十分には喜ばせていないのでは?」という気持ちからやってくる罪悪感です。
通常の子供の親に対する愛は、独占欲の強い親を十分に満足させるほど強くはありませんが、独占欲の強い親の子供は、そのことに罪悪感を抱きます。
また罪悪感は、親の期待に背いたことに対する恐れからやってくる場合もあります。
「親を喜ばせることこそが子供の使命。親が自分の人生で果たせなかった夢や希望を代わりに果たすために子供は生まれてくる」という考え方は、いぜんとして広く行き渡っています。
多くの親は子供が「親の役に立つ者」となることを願っています。
もしも親が成功しなかったとすれば子供は親の代わりに成功しなくてはなりません。
もしも親が愛されなかったのであれば、子供が親を愛さなくてはなりません。
もしも親が人から支配されるばかりで人を支配できないことに不満を感じていれば、子供が親に支配されなくてはなりません。
たとえ子供がこれらの期待に応えたとしても、それでもまだ子供は、十分ではないと感じ「親を失望させている」と、罪悪感を感じがちです。
親のようにはなれない、という罪悪感

当然のことですが、たとえ親子であっても、それぞれの人間の持つ個性や資質は違います。
ところが、自分の親と自分の違う点が、「親を失望させている」という罪悪感を作り出すことがあるのです。
支配的な親は、子供に自分と完全に同じになることを要求し、子供の自分とは違う点をすべて欠点とみなします。
すると子供もやはり、自分の親とは違う点をすべて欠点とみなすようになり、その点に罪悪感と劣等感を感じるようになります。
そして「親のようになろう」と努力します。
けれども、どんなに頑張ってみても単に自分本来の個性と成長を歪め、親のきわめて不完全なレプリカとなるだけです。
それでも、この子供は「親のようにならなければイケナイ」と信じ込んでいますので、このような失敗に良心のやましさを感じます。
もしもこの子が、この種の「親孝行」から自分を解放し、本来の自分自身の個性を伸ばすための努力をしようとしても、「親孝行」をしていないという罪悪感に耐えかね、本来の自分自身の個性や自由を確立する前に、道なかばにして倒れてしまいがちです。
なぜ、この罪悪感がそんなにも大きいのかといえば、子供が親の失望と非難と懇願に対抗しなければならないだけではなく、さらに「親孝行」ということを子供に要求する文化全体に対抗しなければならないからです。
罪悪感が依存心を作る

この「親を喜ばせることが子供の義務なのに自分はそれを十分には果たしていない」という考え方から生まれる「罪悪感」は、人間の依存心を強めます。
実は、罪悪感こそが人間の依存心を作り出し、そして依存心を強化するための最も効果的な手段なのです。
親や国家などの、約束やルールを決める立場にある権威をもつ側の人間は、その権威に従わなくてはならない人々に、非常に厳格なルールを課します
そのルール全てに完璧に従うことは、誰にとっても明らかに不可能であるほど厳格なルールを課すのです。
こうして、権威に服従しなければならない人々は全員、どうしても避けることのできない罪を背負うことになります。
このどうしても避けられない罪よって、権威に従わなければならない人々は、罪悪感と防衛心を抱くことになります。
また、この罪悪感と防衛心は、何とかしてその罪を許してもらいたいという欲求も作り出します。
その「罪を許して欲しい」と願う気持ちが、「許し」を与えてくれる権威に対して非常に大きな感謝の気持ちを作りだします。
この「感謝の気持ち」が、権威の不合理な要求に対して批判的になることを難しくしてしまいます。
権威主義的な関係を強力に結びつけるものは、こうした罪悪感と依存心との相互作用です。
不合理な権威に従うことは人間の意志を弱め、同時に意志を弱めるようなものは全て依存心を大きくします。
こうして一つの悪循環が作り出されるのです。
「自然な欲求は悪いこと」にして罪悪感をつくる

子供の意志を弱くする一番効果的な方法は、子供に罪悪感を植えつけることです。
そのためには、子供の性欲そのものや、子供が性欲を表現した時に、それを「悪い」と思わせさえすればいいのです。
子供は性欲を持たないわけにはいきませんので、罪悪感を植えつけるこの方法は確実に成功します。
親(および親と同じような権威者としての社会)が、性と罪を結びつけることに成功すれば、性的な衝動が起こるのと同じ頻度で確実に罪悪感が作り出されます。
それに加えて、体の他の機能も「道徳的」な配慮によって子供の罪悪感をたかめていきます。
もしも子供が、決められた通りのやり方でトイレに行かなかったり、親が期待するほどはキレイにしていなかったり、お作法通りの食べ方をしなかったりすると、その子は「悪い子」です。
こうして5~6歳になるころには、子供には歪んだ罪悪感が完全にしみ込んでしまいます。
子供の自然な衝動が、親によって「悪い」という道徳的な評価を与えられるため、これもまた常に罪悪感を作り出す原因となってしまうのです。
「その弱い意志こそダメな証拠だ!」という合理化

非合理的な権威としての親が、子供の意志、自発性、独立性などをくじくコトに一度成功すると、子供の罪悪感は、また別のやり方でも強められます。
子供は自分の意志がくじかれたこと、自分が親に負けたこと、本当は納得していないにも関わらず親に従わなければならなくなったこと、などをボンヤリと意識しますが、なぜそうなったのか?それを意味づけなければなりません。
途方に暮れるような苦しい経験を何の説明もなしに受け入れることはできないからです。
ここで子供は「自分の意志がくじかれたという事実じたいが、自分に罪があるという事を証明している」という説明を受けます。
それはインドの最下層のカーストの人々が受ける説明と同じです。
「最下層のカーストに生まれたことじたいが、前世で罪を犯した証拠だ」と説明されるように、「しょせん親にくじかれる程度の弱い意志しか持っていないことじたいが、もともとその意志が本物ではなくイイカゲンなものだった証拠だ」と、合理化されるのです。
自発性はこうやってダメにされます

もしも親が、社会における不合理な権威の代理として、子供の意志、自発性、独立性を破壊しようとすれば、子供は破壊されるために生まれてくるわけではないので、親によって代表されるそのような不合理な権威と戦います。
子供は単に圧迫から逃れ自由になるためだけではなく、ロボットではない一人の人間としての自分自身を確立するために、自由を得ようとします。
この自由を得ようとする戦いにどれだけ成功するかは子供によって違いますが、完全に成功する子供はホンの少しです。
すべてのメンタルヘルス上の問題の奥底には、この不合理な権威との戦いに敗れた子供のころの心の傷跡、トラウマがあります。
これらのトラウマは、ひとつの症候群を作り出しますが、そのうちの重要なものが、独創性と自発性の衰退およびマヒです。
本来の「自分」というものが弱まり、ニセモノの自分がそれに代わります。
「私は私だ」という感情が薄まり、「私」とは、たんに周りの人の期待の反映になってしまいます。
自律性が失われ、他律性がそれにかわります。
不明瞭性、あるいはH.Sサリバンの用語で言えば「すべての対人関係における経験の並列性」が生まれます。
この、本当の自分が弱まりニセモノの自分と入れ替わってしまう過程について詳しくはこちら、をお読みください。→「「普通」になるには、「自分」をやめる必要があります。」
権威に負けて「やましい心」ができる。

以上のような「自分自身のための戦いに負けたコト」による一番重要な徴候は「やましい気持ち」が作り出されてしまうことです。
自分自身をなんとか確立しようと奮闘中の人間が、権威主義の網の目を通り抜けることに成功しなかった場合、権威から逃げようとしたコトそのものが罪の証拠になると思い込まされてしまうので、「やましさがない」状態は、新たな服従によってしか回復されません。
このような形の良心をエーリッヒ・フロムは権威主義的良心と名付けています。
権威主義的良心とは、親や先生や国家など、その時その文化における権威者とされている「自分の外側にある権威」を内面化した声です。
このような権威主義的良心については、道徳的な制裁を考えずに語ることはできません。
この場合の、良心にしたがった行動とは、罰への恐れとご褒美への期待によってコントロールされています。
権威主義的良心に従った行動ができるかどうかは、そこに実際に権威者がいるかいないか、で大きく変わります。
また権威者たちが持っていると称している、あるいは実際にもっている「権威に従わなければならない人々の行動についての知識や、処罰能力、報奨の能力」などによっても変わってきます。
よって、権威者がいなくなったり、人が権威者を恐れる理由がなくなったりすれば権威主義的良心は弱まり威力を失います。
人々が自分の良心から生まれた罪悪感だと考えるような経験も、実際には単に権威にたいする恐れにすぎない場合がほとんどです。
正確にいうなら、このような人々は、本当は罪悪感を感じているのではなく恐怖を感じているのです。
権威主義的良心はこうして作られる

権威的良心というものは以下のような過程で作られていきます。
親や先生、国や世論等の、その人が「これが権威だ」と感じるものを、人間は、意識的にあるいは無意識的に「道徳的なルールを作る人」として受け止めます。
そして、その掟と制裁に服従し、それらを内面化します。
こうして外的権威の掟と制裁が、自分自身の一部となり、人間は自分の外側の何かに責任を感じるのではなく自分の内側にある何か、つまり自分自身の「権威主義的良心」に対して責任を感じるようになります。
権威主義的良心は外的権威にたいする恐怖よりも、さらに効果的に行動をコントロールします。
なぜなら親や世間などの自分の外側にいる権威ならば、それから逃げ隠れすることもできますが、自分自身からは逃げ出すことはできないために、自分の一部になってしまった内面化された権威からも逃げ出すことができないからです。
権威主義的良心はフロイトが超自我とよんだものです。
これは良心の一形式、あるいは良心の発達における予備的段階にすぎません。
権威主義的良心は、たんなる刑罰に対する恐怖やご褒美への希望とは少し違っていて、その人と権威との関係が内面化されてはいますが、本質的な点においては大差はありません。
その最も重要な類似点は、権威主義的良心の命令は、自分自身の価値判断によって決めたものではなく、その命令や禁止が権威者によって与えられたという事実によってのみ決められている、という点です。
もしも権威者から与えられたものが、たまたま「良いもの」であれば、この権威主義的良心も人を良い方向へと導く可能性はあるかもしれません。
けれども、それは「良いもの」であるがゆえに「良心」となったわけではなく、それは権威者によって与えられたという理由で「良心」となったのです。
もしもそれが「悪いもの」であっても、権威者から与えられれば同じように「良心」と呼ばれます。
例えばヒットラーの信奉者は人間性に反する行為をしている時でも自分の「良心」に従って行動していると信じていました。
たとえどんなに「悪いもの」であってもいったんそれを「良心」として内面化してしまえば、完全というものをもとめる人間の欲求が、この「良心」に理想的なイメージを与え、それが実際の権威者(親や先生や国家元首など)に反映されるため、実際の権威者は、その現実の姿よりもずっと理想化されたものとして人間の目に映るようになってしまいます。
よって現実の権威者にどれほど悪い欠点があろうとも、それが目に入らなくなってしまうのです。
権威を喜ばせている時が最高!

権威主義的良心は権威の命令と禁止によって作られています。
ある人の心の中にある権威主義的良心がどれほど強いかは権威に対する恐れと賛美の感情が、どれほど強いかによって決まります。
権威主義的良心を持つ人にとっての「良心のやましさを感じない状態」というのは、「(自分の外側と内側にある)権威を喜ばせている」という感覚であり、「良心のやましさを感じる状態」というのは「権威を喜ばせていない」という感覚です。
権威主義的良心のやましさを感じていない時、権威主義的な人は安心感と幸福感を感じます。
それは権威から認められ、権威のそばにいる、という感覚を与えてくれるからです。
これに対して権威主義的良心にやましさを感じているとき、権威主義的人間は恐れと不安を感じます。
というのも権威の意志にそむくことは権威から罰せられる危険と、さらに悪いことには権威から見捨てられる危険とを含んでいるからです。
この「権威から見捨てられる恐怖」が、どれほど強いものかを十分に理解するためには権威主義的人間の性格を理解する必要があります。
権威主義的な性格の人は、自分より強く偉大だと感じる権威の一部となりその権威と共生することによって安心感をみいだしています。
この人は自分らしさというものを犠牲にして、その代わりに権威の一部分となっています。
そして権威の一部分でいる間は、この人は権威の強さと偉大さを自分は部分的に共有していると感じることができます。
この人が何かを「確実だ」と思える感覚や「自分は自分だ」と思える感覚は、この権威との共生に依存しています。
ですから権威に見捨てられるということは、何一つ確実ではなく、自分が誰かも分からなくなるような「無」の恐怖に向き合わなければならないことを意味します。
権威主義的な性格の人にとっては、どんなことでもこれよりはまだマシです。
もちろん権威によって愛され認められることは、この人に最大の満足を与えますが、罰を受けることでさえ拒否されるよりはマシなのです。
罰を与えるということは権威はまだ自分と一緒にいてくれるということです。
たとえ罪を犯したとしても、権威が罰を与えてくれるということは、少なくても権威がまだ自分を心配してくれているという証拠です。
罰を甘んじて受けることにより、この人は、自分の罪は清められたと感じ、権威に従属しているという安心感は回復されます。
反抗が最大の罪

権威主義的な倫理観において、根源的な罪は権威の命令にたいする反抗です。
つまり不従順であることこそが最大の罪とされ、従順が最大の徳とされます。
従順とは「権威の優れた力と知恵を認め、権威を持つ者が独断で命令し、報いを与え、罰を与える権利をもつことを承認する」ことを意味します。
権威が服従を要求するのは、その力に対する恐れのためだけではなく、権威が持つ道徳的な優越性と正しさが確信されなければならない、からでもあります。
権威に対する尊敬とは、権威に対して疑いを持ったり疑問を持つことじたいを禁止するという意味を同時に含んでいます。
権威は自分のくだす命令や禁止や報酬や刑罰に説明を与えることもありますが、説明をしなくても差し支えはありません。
けれども権威に従う人は、決してそれを疑ったり批判したりする権利を持ちません。
たとえ権威を批判する正当な理由がある場合でも、権威に従う立場の人間は、常に権威より劣った存在だと前提されていますので、そのように劣った人間が、褒めたたえるべき権威を批判するコトじたいが、その人がバカで傲慢であることを表しており、したがって罪がある証拠だ、という事になってしまうのです。
やっぱり平等なんてあり得ない

権威の優越性を承認しなければならないという義務は数々の禁止によって示されます。
その一番大きなものが、権威に従う立場の人間が、自分と権威とを似たようなものと感じたり、自分にも権威者と同じようになれる可能性があると思うことに対する禁止です。
このようなことを許してしまえば、権威の絶対的な優越性と独自性に矛盾することになるからです。
権威主義的な考え方では、「権威者とは、それに服従する者たちとは根本的に異なった者である」と定義されます。
権威者は、普通の人が決して持ちえぬ権力を持ち、服従者たちとは比較にならない飛びぬけた力と知恵を持っているものと考えられています。
権威主義的な考え方においては、権威をもつ人と服従する人との間には、本質的に決して超えられえない差異があるのです。
権威者がもつ独自性の中でも特に重要なのは、権威者はけっして他人の意志には従わず自分の意志によってのみ働き、他人の道具や手段とはならず自分自身の目的を持ち、創造するものであって創造されるものではない、という唯一者としての特権にあります。
権威主義的な考え方では、意志の力と創造力は権威者だけがもつ特権なのです。
服従する人達は権威者の目的のための手段です。
つまり普通の人というのは権威者から利用される道具であり権威者の所有物なのです。
幸せになることに権威主義は反対します

人がロボットであることをやめて「何かを創り出す人:何かを生み出す人」になろうとすれば権威者の主権は脅かされます。
何かを生み出し創り出すことは、人間の強さと幸福と自由の源です。
しかし、人が自分を超えたなんらかの大きな力に自分は依存していると感じている間は、なにか自分独自のものを生み出そうとすること、つまり自分の意志を主張することに、罪悪感を感じてしまいます。
服従する立場にいるはずの人が、自分の意志を主張することは、常に権威者から「傲慢、憎むべき個人主義」と非難されてきました。
服従する者の義務は、自分を捨て権威者の道具となることだ、という「滅私奉公」的な確信が、自分の意志を主張することそのものに罪悪感を感じさせ、それを抑え込もうとさせます。
逆説的な言い方になりますが、権威主義的な良心を持つ人にとっては、自分自身の有能さや強さやプライドや独立性を感じている状態は「良心にやましさを感じる」状態であり、逆に自分をさげすみ、自分の無力を感じ、自己嫌悪を感じるときが「良心にやましさを感じていない状態」となってしまうのです。
このようにして権威主義的良心は「努力できない病」を根本的に克服するために必要な「人間的良心」を発達させようとする時の、ジャマになってしまいます。
人間的良心について

では人間的良心とはどのようなものでしょう?
それは権威主義的良心のように、私たちがそれを喜ばせようと熱中したり、喜ばせないことを恐れたりするような権威を内面化した声といったものではありません。
それは、本当の自分自身の声であり、外部からの制裁や賞賛からは独立したものです。
では、この声の本質とはなんでしょう?
なぜ私たちはその声を聴くことができるのでしょう?
また逆に、なぜその声にたいして耳をふさぐことができるのでしょう?
人間的な良心とはどのようなものか?を知るために、まず人間の全歴史において、正義や愛といった人間の理想が、どのように守られてきたのかを考えてみたいと思います。
歴史を振り返えってみれば、人はその人間的な良心に従って行動することにより、自分たちの知識や信念を押しつぶそうとするあらゆる迫害に対抗して、正義や愛といった理想を守り続けてきたことが解ります。
聖書の中の預言者たちが、自分の祖国を非難し、それが堕落と不正のために滅びると予言したとき、彼らは自分のなかにある人間的な良心に従って行動したと言えるでしょう。
またソクラテスは真理をまげて、自分の人間的な良心を裏切るよりはむしろ死を選びました。
もしも人間的な良心というものがなければ、人類はその危険な道をたどりながら、とっくの昔に泥沼の中へ、はまり込んでしまったことでしょう。
このような人間的な良心に従って行動する人々とは違って、権威主義的良心に従って行動する人々もいます。
つまり人間的な良心をもった人々を処刑する宗教裁判をやった人達も、やはり権威主義的な良心という自分たちの良心の名においてやったのだと言っています。
侵略戦争の張本人たちもまた、何よりも自分の権力欲の満足を第一にしながら、自分たちの良心にしたがって行動する、と言います。
実際に、他人や自分自身への様々な残虐行為や非道な行為が、良心の命ずるものだと合理化されてきました。
同じ「良心」という名で呼ばれるモノであっても、人間的良心と権威主義的良心には大きな違いがあるのです。
人間的な良心と権威主義的な良心の違いについて考えるためには、良心に関する哲学的文献も、豊富な手掛かりを与えてくれます。
キケロやセネカは、良心を「われわれの行為を道徳的であるかどうかという観点から非難したり、弁護したりする内なる声」と、定義しています。
これは権威主義的良心にも、人間的良心にもあてはまる定義ですが、どちらかと言えば権威主義的良心に近い定義でしょう。
ストア哲学ではそれを自己保存ということ(自分自身に配慮すること)に関係づけ、クリッツシポスはそれを「内なる調和の意識」だと言っています。これは人間的良心の定義です。
スコラ哲学においては、良心とは「理性の法則」だと考えられていて、良知良能(synderesis )とは区別されています。
良知良能とは「正しさを求める性質(あるいは能力)、および正しいかどうかを判断をする性質(あるいは能力)」であり、良心とは「大枠での正しい原理を個々の行為に適用するもの」とされています。
このスコラ哲学における良知良能は人間的良心の定義と言えるでしょう。
この良知良能(synderesis )という言葉は近代以降はあまり使われなくなりましたが、かわりに良心という言葉が、スコラ哲学における良知良能という意味で、つまり「道徳的な法則について心の内で気づくこと」という意味でしばしば使われています。
このような「気づくこと」の中にある感情的な要素はイギリスの思想家たちによって強調されてきました。
たとえばシャッフルベリーは、人には「道徳的感覚」というものがあると仮定しました。
つまり、人間には、その行為が道徳的に正しいか間違っているかを感情的に判断する感覚が存在すると仮定しました。これも人間的良心の定義と言えるでしょう。
バトラーは道徳原理を人間のなりたちに本質的なものとし、そして良心をとくに「情け深い行為をしようとする内面的な欲求」と同一視しました。これもまた人間的良心の定義の一つになります。
アダム・スミスの良心の定義はハッキリとした権威主義的良心の定義です。
それは「他人にたいする私たちの感情と、他人の賛同や非難に対する私たちの反応が良心の核だ」としています。
カントは良心を、すべての特殊な内容から抽象的に取り出し、それを義務そのものであるとしました。これは権威主義的良心にも人間的良心にも、あてはまる定義です。
宗教的な「やましい心」を痛烈に批判したニーチエは、「真の良心とは自己肯定である」と定義しました。
つまり、良心とは「自分自身に「良し」と言える能力」に基づくモノである、と定義しました。これはまさしく人間的な良心の定義です。
マックスシェーラーは、良心を合理的判断としました。けれどもそれは思考的な判断ではなく感情による判断であると考えました。これも人間的良心の定義となります。
さらに人類は、ここ5~6千年の歴史の中で、様々な宗教や哲学、例えばキリスト教、イスラム教、仏教、道教、あるいは古代ギリシャ哲学等々を発展させ、それらの中で、人間的な良心と関係の深い道徳的な規則を作り上げてきました。
それぞれの宗教や哲学においては、共通の中心点よりも相違点が強調される傾向が高いのですが、人間の立場からすればこれらの教説における共通点は、相違点よりもはるかに重要です。
もしもこれらの教説や哲学の限界やこじつけを、そのような思想や宗教が表れた特殊な歴史的、社会的、経済的、文化的状態の結果だと理解するなら
すべての宗教家や思想家の目的は、「人間的良心を発達させることによって、人間が自分自身をより成長発展させることができるようにすることであり、その成長発展によって人間が自分自身をより幸福にすることである」という驚くべき一致を見いだすことができるのです。
人間的良心とは?

以上の文脈から人間的良心というものを定義するなら、それは以下のようなものになるでしょう。
人間的良心とは、私たちが人間特有の機能を発達させた場合や、逆にその機能が衰退した場合の特徴としてあらわれてくる、私たちの全人間性にたいする反応です。
それは、あれやこれといった一つ一つの能力に対する反応ではなく、私たちの人間としての、そして個人としての「自分」を、作り出すための全体的能力に対する反応です。
人間的良心は、私たちの人間として機能を判定します。
それは内なる自分自身についての知識であり、生きるという技術においての成功と失敗を知る知識です。
しかし人間的良心が知識であるとはいっても、それは単なる抽象的な知識ではありません。
それは感情的な性質をもっています。
なぜなら、それは私たちの全体的な人間性にたいする反応であって、単なる理性だけの反応ではないからです。
実際、人間的良心が語る言葉に気づいていなくても、人間的良心からの影響は受けています。
人間本来の特質に合うように、そしてその人個人の本来の特質に合うように、自分自身を成長発達させるために役立つ全ての行動や考え方や感情は、人間的良心における「やましくない心」の特徴である内的な承認感、内的な「これで良し」という感覚を生み出します。
その反対に、私たちの全人間性と自分の個性に有害な、行動も考え方も感情も、人間的良心における「やましい心」の特性である、落ち着かない、不愉快な、イヤな感覚を引き起こします。
良心は本当の自分の声です。

人間的良心とは、私たち自身対する私たち自身の反応です。
それは私たちの本当の声であり、私たちを私たち自身に呼び戻し、私たちを創造的に生きさせようとするものです。
私たちが潜在的に持っている可能性を、完全に調和的に発展させ実現させようとする声です。
それは「本当の自分」の守り神です。
それはニーチェの言葉で言えば「人が正当な誇りをもって自分自身を保障する能力であり、同時に自分自身に対して「良し」と言うことのできる能力」です。
もしも愛するということが、愛する人の可能性を確信し、その人だけがもつ独自性に配慮をして、それを尊敬することだとすれば、人間的良心とはまさしく私たち自身に対する私たちの愛にみちた配慮の声だということができるでしょう。
人間的良心とは、私たちの本当の姿の表現というだけではありません。
それはまた人が生きる上での道徳的経験の本質を含んでいます。
人生の目的と、その目的を達成するための法則に関する知識を、私たちは人間的良心の中にもっています。
人生の目的とその目的を達成するための法則とは、私たちが先人から学び、また自分自身でもそれが真理であることを発見し、「これが正しい生き方だ」と、心から納得したものです。
良心が幸せを作ります。

また人間的良心とは、私たちが自分自身の「人間としての利益」を追及するという意味での自己愛であり、私たちが潜在的に持つ完全性の一つの表現でもあります。
(「人間としての利益」とは何かについてはこちらをどうぞ→「ジコチューはモラルが高い、場合があります。」)
人間的良心の目標は「生み出す力:創造性:生産性」であり、従って「幸福」です。
なぜなら幸福とは、創造性(生産性)をもった生活(=何かを創り出す生活)に必然的に、ともなうものだからです。
私たちの人間としての性質と、それぞれの個人個人に特有なその人独自の性質の、統一性や全体性に反するものはどんなものでも、考え方でも行動の仕方でも食べ物の好みや性行動についてさえ、すべて人間的良心に反する行動です。
一方、権威主義的良心は、人間の服従や自己犠牲や、義務、あるいは「社会的適応」にしか関係していません。
たとえ、それがどんなに立派なものに見えても、他人の道具になって自分をダメにすることや、自分自身を失うことや、不幸であること、諦めること、失望、などはすべて人間的良心の要求に反するものです。
けれども以上のような人間的良心についての分析は、多くの人々にとって人間的良心の声がきわめて弱く、その声を聞くことも、その声に従うこともできない、という事実と矛盾するように思われるかもしれません。
これこそが、人が自分にとっての正しい生き方をすることが難しくなり、不安定になってしまう原因です。
もしも人間的良心というものが、常に声高くハッキリと語ってくれるものであれば、自分にとっての正しい生き方への道を、踏み誤る人はホンの少しでしょう。
この疑問にたいする一つの解答は、人間的良心の性質によって答えられます。
人間的良心の機能は私たちの「人間としての利益」を守ることにあるのですから、人が「人間としての自分」というものを完全に失ってしまい、自分の「人間としての利益」にたいして完全に無関心になり、一人の人間としては破壊されてしまっている場合、人間的良心は生きることができないのです。
人間的良心と、人間の「生み出す力:創造性:生産性」との関係は一種の相互作用です。
人間が、創造的に生きれば生きるほど、人間的良心はますます強められ、また逆に人間的良心が強くなればなるほど創造性も高まります。
生き方が創造的でないと、人間的良心は弱まります。
人間にとっての悲劇は、人が人間的良心をもっとも必要とするときに、それがもっとも弱まっているということにあります。
また、私たちが人間的良心の声を上手く聞くことのできない更に重要な理由は、私たちが、その声を聴くことを避けようとするコトにあります。
そのうえ問題になるのは、どうすれば人間的良心の声を聴くことができるのかを、私たちが知らないという事にもあります。
人は、しばしば自分の良心が大声で語り、その言葉をハッキリと聞き取ることができるだろう、という幻想を抱いています。
けれども、そのような声を待っている人たちは、最後まで何も聞こえません。
人間的良心の声は、かすかであり、その言葉はハッキリとしません。
よって私たちが人間的良心に従って行動するためには、人間的良心の伝える言葉をどうやって聞きとり理解するかを学ばなくてはなりません。
自分の人間的良心の言葉を理解できるようになるのは、極めて難しいのです。
その理由は主に二つあります。
まず一つ目の理由は、私たちが自分自身の声に耳を傾けることができない、という点にあります。
人間的良心の声を聴くためには、まず自分自身に耳をかたむけなければなりませんが、これこそが、多くの現代人にとって非常に難しいことなのです。
私たちは、あらゆる声、あらゆる人に耳を傾けますが、ただ自分自身に対してだけは、決して耳を傾けません。
私たちは四方八方から押しよせてくる、いろんな意見や考え方などの騒音に、たえずさらされています。
スマホ、インターネット、テレビ、ラジオ、映画、雑誌、新聞、おしゃべり等々…。
たとえ「自分の声には一切耳をかたむけないぞ!」と意図的に努力したとしても、こういった状況以上に、それをうまく達成することはできないでしょう。
自分自身に耳を傾けるためには「自分一人でいて何もしないでいられる能力」が必要なのですが、これこそが多くの現代人が失ってしまっている能力なのです。
私たちは「孤独恐怖症」という病気にかかっています。
私たちにとって、どれほど最低でイヤな人と一緒であろうと、どんなにクダラナイ無意味なコトをしていようと、一人きりで何もしないでいるよりはマシなのです。
私たちは本当の自分自身と向きあうことを恐れているのかもしれません。
自分自身とは、それほど、つきあいにくい人間なのでしょうか?
この、自分自身と向きあうのを避けようとする恐怖は、昔は良く知っていたのに今では得体のしれない人になってしまった古い友人に会う時に感じるような一種の当惑感に近いのかもしれません。
私たちは怖くなって逃げ出します。
こうして私たちは自分の声を聞く機会を逃し、自分の人間的良心を知らずに過ごします。
私たちが自分の人間的良心の声を聞くことが難しくなってしまうもう一つの理由は、人間的良心が、私たちに直接は語りかけず、間接的にしか語りかけないという点にあります。
私たちは、自分を悩ませるものが自分の人間的良心なのだというコトに気がつきません。
無視されているということに対して、もっとも良くみられる人間的良心の反応は、ハッキリとしない漠然とした不安感や罪悪感、あるいは倦怠感や疲労感です。
私たちはこのような不安感や罪悪感、倦怠感や疲労感を、病気のせいにしたり仕事のせいにしたり、やるべき課題をやっていない罪悪感として合理化したりしますが、実際には人間的良心が発している声である場合も多いのです。
けれども、たとえ無意識ではあっても、自分自身の人間的良心の声を無視しつづけることに対する罪悪感が非常に高まり、表面的な合理化ではどうしてもその声を黙らせることができなくなると、深く激しい不安や、肉体的あるいは精神的な病気として現れる場合もあります。
このような不安の一つの形は、死にたいする異常な恐怖です。
それは死を思う時に誰もが感じるような通常の恐怖ではなく、日夜、憑りついて離れないような死への恐怖です。
それは自分の人生をムダに使い、自分のもっている様々な人間的能力を創造的に用いなかったことに対する私たちの人間的良心の「やましさ」の現れなのです。
もちろん死ぬことは、誰にとっても非常に辛いことです。
けれども「本当の自分としては一度も生きたことがなく死ななければならない」と感じるのは、人間にとって耐えられるものではありません。
この不合理な死の恐怖と関係が深いのが、老化にたいする恐れです。
通常の、老化にたいする不安というものも当然ありますが、老化することをまるで悪夢のように激しく嫌悪する強い恐怖心をもつ人々がいます。
このような人々を精神分析してみると、この人たちは肉体的な力が弱まることが、感情的な能力や知的な能力が弱まるコトと直接つながっていて、年をとれば人間的としてもダメになってしまう、と確信していることが解かります。
このような考えは迷信と変わらず、きわめてハッキリとした反対の事実があってもなお、この考え方は固執されるのです。
これは現代の「速さ、順応性、肉体的活力」といった、いわゆる若さというものが特に価値あるものとされる考え方によって、さらに助長されます。
このような能力は人間の人格的な発展のために必要な能力であるというよりも、競争に勝つために必要な能力です。
けれども老人になる前に、創造的に生きていた人々は、たとえ年をとっても、精神面そして感情面では、けっして弱くはならないことを多くの事実が物語っています。
逆に、創造的な生き方の中で発達させた精神的、感情的な能力は、肉体の活力が衰えてもなお成長し続けるのです。
若い時代を創造的に生きてこなかった人は、その人の活動の源泉であった肉体の力が枯れてしまうと全体的な人間性もダメになってしまいます。
老年期において全人格が衰退するというのは、実は一つの病的徴候なのです。
それは創造的に生きてこなかった証拠です。
老化たいする病的な恐怖心は、創造的に生きていないことからおこる無意識の感情の表現です。
それは私たちが自分自身を破壊しつづけることに対する、私たち自身の人間的良心の抗議の反応なのです。
死や老化にたいする不合理な恐怖のように印象的ではありませんが、非難されることに対する恐れも、同様に重要な、無意識のうちにおこる人間的良心の罪悪感の表れです。
人間はもともと仲間に受け入れられることを望むものですが、多くの現代人は「すべての人」に受けいれられることを望むのため、自分の考え方や、感情や、行動において、ホンの少しでも「普通」から外れることを恐れます。
この非難されることについての不合理な恐れの理由の一つが、人間的良心にたいする無意識の罪悪感です。
もしも人が創造的に生きることに失敗して、自分自身に「良し」というコトができなければ、他人から「良し」と言ってもらう必要があります。
この、周りからの承認を病的に強くもとめる欲求は、これを人間的な良心にたいする罪悪感の表現としてみるとき、はじめて十分に理解できます。
けれども、このように「死にたいする異常な恐怖」や「老化にたいする異常な恐怖」「周りからの否定にたいする異常な恐怖」といった代償を払うならば、人は一生、自分の声に耳をふさぎ、自分の人間的な良心の声をまったく聴かないで生きる事ができる、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、そのような企てがすべて失敗してしまう一つの状態が人間にはあります。
それは眠っている状態です。
眠っている時、人は昼間悩まされる騒音から遮断されて、その内面の体験だけを感じます。
眠りとは、人がその人間的良心の声を黙らせることができない唯一の状況です。
けれども悲劇は、私たちが自分自身の声を聴くときには眠っていて行動することができず、行動できるときには夢の中では知っていた事を忘れている、という点にあります。
以上の良心に関する議論において権威主義的良心と人間的良心を別々に述べましたが、この二つの良心は、現実には一人の人間の中に混在しています。
ほとんどの人がこの2種類の良心をもっています。
問題はどちらが強力か、またその二つの関係がどのようなものであるかをハッキリと知ることです。
権威主義的良心の顔をしている人間的良心

私たちが「親孝行をしていない」という理由で感じる罪悪感を、私たちは権威主義的良心として経験しますが、その罪悪感を感じさせている本当の原因は実は人間的良心のやましさからきているというケースもあります。
この場合、権威主義的良心は人間的良心のいわば合理化です。
意識的には「親や世間などの権威者の意向にそむいているために自分は罪悪感を感じている」と思うかもしれませんが、実は「本当の自分のために生きていない」がゆえに、無意識の部分で罪悪感を感じている場合も多いのです。
例えば
音楽がとても好きで音楽家になりたいと願っていた男性が、父の希望をかなえるため自分の夢をあきらめ父の会社を継ぎました。
彼の経営手腕は素晴らしいものとは言えず、父親は彼の仕事ぶりに失望し不満をもらしました。
この息子はウツ状態になり、また自分の経営者としての能力にも自信がもてず、精神分析家のもとへやってきました。
分析を受けながら、この息子は自分の虚ろな気持ちや、憂鬱な気分について長々と語ります。
すぐに彼は自分のウツが父親を失望させているという罪悪感を原因としている、と思い当たります。
けれどもそれまで彼の話を聞いてきた分析家が、そのウツの本当の原因について疑問を投げかけると患者は少し戸惑います。
しかしその後すぐに、この患者は、自分が成功した経営者として父親にほめられている夢をみます。
こんなことは現実の生活ではなかったことです。この夢の中で彼は、夢をみながら突然狼狽し自殺しようとする衝動におそわれ、目を覚まします。
彼はこの夢にビックリして「私は、自分の罪悪感の本当の原因を知らないのかもしれない」と考えるようになります。
それから彼は、自分の罪悪感の本当の原因は、父親を失望させたコトにあるのではなく、逆に父に従ってしまい自分が本当に好きだった音楽を捨ててしまったコト、つまり自分自身を失望させたコトにあると、発見します。
彼の意識的な罪悪感は、彼の権威主義的良心の表現として十分に、もっともらしいものでした。
そのせいで彼は、自分の本当の罪悪感、人間的良心の罪悪感の大半を、権威主義的良心が包み隠していたことに、その時まで気づかなかったのです。
この抑圧の原因をみつけるのは簡単です。
現代の文化はこのような抑圧を支持します。
現代社会においては「父親を失望させることに罪悪感を感じる」という考え方は、ほとんどの人にとって理解しやすい考え方なので、誰にとっても意識しやすいのです。
けれども「不本意ながらも父に従ってしまい、自分自身を裏切ったことに罪悪感を感じる」という考え方は、そのような考えに賛同しない人も多いため、誰にとっても意識しやすいとは言えないのです。
またもう一つの理由は、彼が自分の罪悪感の本当の原因に気づいてしまうと、怒った父親に対する恐怖と自分自身を満足させようとする試みの間を揺れ動く代わりに、父親から自分を解放し、自分自身の人生を真剣に生きなければならなくなるという恐れからも、やってきます。
また権威主義的良心と人間的良心のもう一つの関係は、その道徳的な規則の内容が一緒であっても、それを受け入れる動機が違う、という場合です。
たとえば「殺すなかれ、憎むなかれ、ねたむなかれ、隣人を愛せ」などの道徳的な規則は、人間的良心の規則でもあり、権威主義的良心の規則でもあります。
良心の発達の第一段階においては権威が命令を与えるといえるかもしれませんが、後には権威への服従という理由によってではなく、自分に対する責任という理由で、人はその規則に従うようになります。
もしも、良心の発達の第一段階において、あまりにも強大で不合理な権威に基づいた権威主義的良心が作り出されてしまうと、その人のその後の人間的良心の発達はほとんど抑えられてしまいがちです。
そうなると人は、自分の外側にある権威に完全に依存するようになってしまい、自分自身を尊重したり、自分に責任を感じたりすることができなくなってしまいます。
この種の人にとって問題なのは結局、権威に認められるか認められないか、ということだけです。
親も国も世間も同じように強力な権威となりえます。
人間的良心においてはもっとも不道徳な行動ですら権威主義的良心においては「義務」として経験されることもまれではありません。
この二つの良心に共通の「ねばならぬ」という感情は、人間にとっての最善なものにも最悪なものにも関係することができますので当てにはなりません。
良心は社会と文化の中で発展する

これまでの権威主義的良心と人間的良心の説明から誤解されがちなのが、権威主義的良心は文化的伝統の中で作られるのに対して、人間的良心は、そういうものとは無関係に発展する、少し神秘的な種類のもの、いう理解です。
決してそうではなく、この人間的良心とは、人の話す力や考える力と同様に、基本的には生まれながらに持っている能力でありながら、同時に社会や文化の中でのみ発達するものです。
では、具体的にどうすれば人間的良心をより発達させ「努力できない病」を根本的に克服することができるのか?
それについては「がんばれない、努力できない、を治すたった一つの方法」をご覧ください。